剪定には4種類の刃物を準備する おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 剪定を始める前に、はさみなどの必要な用具をそろえ、すぐに使えるように1箇所にまとめて並べます。 枝を切るために使用する刃物は大きく分けるとつぎの4種類です。?植木ばさみ 一番一般的なはさみ、葉や細い枝を切ります。?剪定ばさみ 柄の内側にばねがはさみこまれ、ばねで広げ られた柄を握る力を利用して枝を切ります。?刈り込みばさみ 玉ものや生け垣などの仕立てものの刈込 みに使うはさみ。?のこぎり 太枝を切るときに使います。刃渡りが30?く らいで刃先が丸く、目のあらいものが家庭向きです。 | |
| この記事が掲載されているホームページ/ブログ |
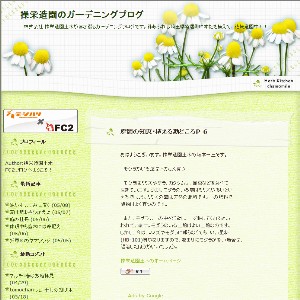 | 操栄造園土木のガーデンブログ 株式 |
| このホームページ/ブログからの最近の投稿 |
ウツギは初夏に花咲く生垣として仕立てる おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 唱歌「夏は来ぬ」の謡だしを思い出してください。「卯の花の匂う垣根に・・・」という歌詞がありますが、この卯の花はウツギのことです。 ここで歌われているように、ウツギは昔から垣根すなわち生垣として使われてきました。 ウツギの花期は五月頃、白い小さな花が優美に垂れ下がる枝に多数つきます。花びらの多い白花ヤエウツギ、花びらの背面が淡紅色のアケボノウツギなどの品種もあり、いずれも芽吹きがいいので、刈り込んで生垣として仕立てることができます。 | |
毎年花を咲かせるために おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 アセビは、前年に新枝の頂部から花穂を伸ばし、四月頃に花をつけます。 毎年、確実に花を咲かせようと思ったら、花後できるだけ早く花穂を切り取ること。 そのままにして結実させると木が疲れ、翌年の花つきが悪くなります。 | |
適切な植え場所と剪定 おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 アセビは、植え場所を選ぶことが大切です。強い日差しを好まないので、一日中、日が当たる場所は避けること。特に西日が直射するところは禁物。だからといって、ほとんど日が当たらない場所でも思うように生育しません。 たとえば石組みに添えたりすると、石の陰で半日蔭になるうえに、石との調和で雅な風情をつくることができます。 アセビは、株立ち状の自然の趣を大切にする木なのであまり切りつめて樹形を壊したくないです。内部の枝がからんで不恰好に見えるときは、車枝状に伸びている枝を一、二本つけ根から間引き、目につく徒長枝があれば元からはずす程度が適当です。 | |
アセビの魅力 おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 アセビは、ご承知のように漢字で「馬酔木」と書きます。アセビには毒があり、馬が食べると酔ったようになることから、この字が当てられています。 アセビは春、花穂に房なりの小花が控えめに咲きます。在来種の花色は白ですが、紅色やピンクの花をつける品種もあります。特に最近出回っているアカバナアセビ(花色はピンク)は、現代建築や洋風庭園によく調和するため、ガーデンニング愛好家に人気が高いようです。 玄関前や門まわり、堀際の植栽に用いても明るい雰囲気をつくります。 | |
アジサイは荒療治で株を更新 おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 アジサイは、あまりに大きくなりすぎてもてあますようであれば、荒療治になりますが、すべての枝を地際から間引きます。 しばらくの間、花は見れませんが、数年もすると、株も小さくまとまるし、花も楽しめるようになります。 すべての花を犠牲にするのに抵抗がある場合には、今年、半分を切り、残り半分は翌年に切るというように二年がかりで行うとのも手です。 その際は今年花をつけた枝を切り、つけなかった枝を残します。残した枝は翌年の花を用意しています。 | |
樹形を小さくまとめるには おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 アジサイは、成長が早く、かつ株立ち状なので、すぐに大きくなり横に広がります。かなり場所もとり、他の木の邪魔になることも少なからずあります。 切りつめて小さくまとめればと思われるかもしれませんが、そうもいかないところにアジサイの難しさがあります。 しかし、鬱蒼と茂り極端にかたちが乱れるようであれば、剪定しなくてはどうしょうもありません。 そんなときは、冬に長く伸びている古い枝を、地際で間引いて新しい枝に更新します。あとは、根元から出ている姿を乱している枝をはさむ程度にとどめます。 | |
アジサイの七変化 おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 アジサイは、七変化という別名があるように咲いているうちに花色が変化します。 (土壌が酸性だと青、アルカリ性だと赤紫)。 雨にそぼぬれる花の風情は、梅雨時のわずらわしさをひととき忘れさせてくれます。 | |
タケとササの違いは? おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 ところで、タケとササの違いをご存じでしょうか?一般には大きく成長するものがタケ、成長しても大きくならないのがササと理解されているようですが、植物分類学上はちがいます。 植物分類学上では「タケノコが成長するにつれて皮を落とすのがタケ、皮をつけたまま成長するのがササ」とされています。 これは少々わかりづらい定義ですが、私たちの間では、あまり意味がありません。 庭木として扱う場合は名前は「タケ」とついたらタケ「ササ」トついたらササと解釈したほうがよいように思います。 | |
ササ類の手入れ おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 ササ類には、クマザサ、コクマザサ、チゴザサなどの種類があります。よく下草などに利用し、和風の景観をつくるのにかかせません。 ササを手入れするにあたって、私たちは五月の初め頃に芯芽(まだ開かずに巻いている葉)を一つ一つ抜いて前年と同じ高さにそろえるようにします。 これは非常にていねいな仕事ですが、じつに手間のかかる作業です。 ですから手軽にきれいにしたい場合は、刈り込みで整えるといいでしょう。 | |
三節どめで剪定 おはようございます。操栄造園土木の坂本一三です。 タケ、特にナリヒダダケやクロチクは、大名竹に仕立てられることがありますが、やはり自然樹形の美しさを大切にしたいと私たちは思います。 ただし、放っておくと枝葉が茂りすぎてむさ苦しくなるので、適度に枝抜きをして透かしてやる必要があります。 風に揺らいでさわさわと葉ずれの音が聞こえるような感じが一番いいのです。 タケの剪定は、六〜七月が適期。冬に下手にいじると、枯れてしまうおそれがあります。昔から「タケは、三節どめではさむ」と言われています。 | |

